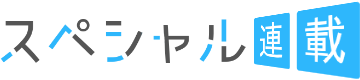「海陽版ディスカバリーメソッド」とは
今、教育界で話題になっている「非認知能力」というスキルをご存じですか。テストや通知表では測りきれないコミュニケーション能力や協調性、粘り強さ……変化の激しい社会へ子どもたちを送り出すために、この「非認知能力」を育てることが課題となっています。


非認知能力の育成に関して、海陽は全国の学校を一歩リード! 「毎日の寮生活をもっと楽しくするためにはどうすべきか」を生徒自身が考え、実行していく。その中で成長できるようにさまざまな工夫がされています。
そのひとつが今回ご紹介する「海陽版ディスカバリーメソッド」です!こちらは、Z会と共同開発した「生徒が自分自身を見つめ直す」ための指導方法。具体的にどのような授業が行われているのでしょうか。

ある日、海陽で中学3年生を対象とした特別ワークショップ「NASAゲーム」が開催されました。その内容はディスカッションを中心にしたもので、議題はこのようになっていました。
あなたは宇宙飛行士です。月面で遭難してしまったあなたはリストから10個のアイテムを選んで基地まで向かわなくてはなりません。基地までは200マイルの距離があります。
想像力や科学的な思考力が試されるこちらの問いを、生徒たちはグループになって話し合います。その結論を出してから、生徒たちにはこんなチェックシートが配布されました。

実はこちらのワークショップは「海陽版ディスカバリーメソッド」の一環。同時に社会に出てから活躍するための土台となる力が自己評価しやすいように示してあります。なかなか「非認知能力」の伸びに気づくことは難しいものですが、こうしたツールがあると便利ですね!
生き残れ!そして辿りつけ!月面の冒険をイメージ
そちらのワークショップについて生徒に聞いてみました。中学3年生のお二人です。どんな話し合いをして、その過程をどう自己評価したのでしょうか?


ワークショップ「NASAゲーム」の中で話し合ったことを教えてください。
森くん 月面で遭難してしまったという状況を思い浮かべて、「とにかく今生き残るために必要なもの」「基地に行くために必要なもの」それぞれを考えるという二つの課題を設定して話し合いを進めました。
峯村くん アイテムの関係性についても踏まえて、アイデアを出し合いました。例えば、「酸素が充分にないとマッチがあっても意味がない…じゃあ酸素ボンベが欠かせないね」というような流れです。一人ひとりの違った意見をチームの総意へとまとめあげていくという流れでした。

チェックシートで振り返った項目と照らし合わせて、ワークショップの中で良くできたポイントを教えてください。
森くん 競争ではなく協力を求める項目があって、そこは達成できたと思います。「ほかのメンバーの考えがもっと論理的であれば受け入れる」ということができました。
峯村くん コミュニケーション能力の項目は高めに自己評価をしました。一人だけ周りと対立する意見を出すメンバーがいたのですが、彼の意見を受け止めることで科学的な合理性を慎重に考えるきっかけができました。

反対に反省点を教えてください。
森くん チームをまとめるうえでもっと先入観をなくせたのかもしれないという思いはありましたね。
峯村くん 効率性に関する項目については、なかなか高く評価できませんでした。もっと話し合いをテキパキ進められたかもしれない。そんな気がしています。
チェックするたび、自分が見えてくる!一歩ずつの成長
こうしたチェックシートを使った振り返りは定期テスト、文化祭・運動会などの行事、校外学習の機会にも行われます。NASAゲームを通して、将来活躍するためにどんな力が必要なのか理解を深めた生徒たち。各イベントのタイミングで、自己を見つめ直す習慣が身についたようです。
学校生活のいろいろな場面で振り返りをすることで、自分自身に生じた変化を教えてください。
森くん 定期試験に合わせて、もっと自己管理をしていこうという気持ちが生まれて、ちゃんと達成可能な目標を設定できるようになりました。ほかにも、行事の運営に参加したときに、うまくいかないことがあっても感情的にならなくなりました。
峯村くん もともと小学生のときまで部屋が汚かったのですが、自然と片づけをするようになりました。早寝早起きの習慣もできましたし、イライラしにくくなった気もします。

チェックシートで示されているスキルは日常生活のどのような場面で試されますか。
森くん 寮の中で問題が起きて、その対処をするときですね。ちゃんとみんなで責任ある行動をとれるかにシートで示されていることが関わってくると思います。
峯村くん 自由な寮生活を送るには自分たちの責任を果たすこと。その前提を守ることができれば、あえて厳しいルールをつくる必要がなくなります。さらに楽しい寮生活を送る。その目的に向かって、みんなで自分を見直しつつ生活しているのが海陽学園です。
「先生の想定を超えるレベル」へと成長を後押し!
「海陽版ディスカバリーメソッド」の統括を担当する武田眞史先生(数学科)からもご紹介いただきました。

「海陽版ディスカバリーメソッド」での指導内容を教えてください。
武田先生 生徒からご紹介したようなワークショップ、振り返りのほか、座学の講座も用意しております。生徒が自身の行動を反省するセルフチェックだけでなく、「こういう場面ならどう行動しますか」と問いかけるスキルチェックも実施し、その結果を照らし合わせてスコア化しています。自分のあり方を客観的に捉えることができる仕組みになっています。
チェックシートの項目がどのように設定されているかを教えてください。
武田先生 身につけてほしいスキルを行動から測る指標を、私たちは「行動マーカー」と名付けています。もともとのZ会によるバージョンでは、全96項目あったので、寮生活を送ること、学年に応じた項目数にすることを踏まえて、海陽版を設定しました。中学1年生は自己管理と集団行動に関する内容がメインで19項目、それが学年に応じて無理がないようにだんだんと増えていく仕組みです。
「海陽版ディスカバリーメソッド」による振り返りを通して、生徒はどう変わりますか。
武田先生 新しくできるようになったこと、自分が苦手とすることをしっかり自覚できるようになります。たくさんの経験を行動マーカに紐づけて捉え直すなかで、成長するための糧が見つかるからでしょう。必ずしも行動マーカで示されている内容が正解とはかぎらない場面も出てくると思います。そのときに自分で考えて最善の行動を取れるようになってほしいですね。私たち教員の想定を超えるレベルまで成長してほしいと願っています。

編集後記
海陽は新しい時代のリーダー育成を目指す学校。高い目標に向かって、生徒が自分自身で歩き出せるように後押しします。多彩な体験活動についても、学校公式サイトでチェックしてみてください。
イベント日程
| イベント名 | 実施日時 |
|---|---|
| 適性検査型入試説明会・練習会(東京会場) | 7月8日(土)10:00~11:30・13:00~14:30 |
| 宿泊体験入学 | 7月22日(土)13:20~翌23日(日)11:00 |
| 宿泊体験入学 | 7月28日(金)13:20~翌29日(土)11:00 |
| 宿泊体験入学 | 7月29日(土)13:20~翌30日(日)11:00 |